事業承継と事業譲渡・会社分割

目次
1 社長(オーナー)が事業承継を考えるきっかけ
社長(オーナー)が事業承継を考える1つのきっかけとして、会社経営が苦しくなる状況下において会社再建を後継者に託したいという場合があります。ただ、こういった場合、会社の資金繰り等が悪化していることが多く、なかなか後継者を見つけることができないという問題が起こります。
そこで、会社をそのまま引き継がせるのではなく、会社にある優良又は有望な一事業部門のみを第三者に引渡し、残った事業部門を含む会社については清算を図ることで、事業承継を行うという方法が最近では多く行われるようになっています。
このような一事業部門を第三者に引渡す法的制度として、事業譲渡(営業譲渡)と会社分割が考えられます。
事業譲渡について
まず、事業譲渡(営業譲渡)ですが、事業を一種の商品に見立てて、事業を売買の対象とするという手法となります。この事業には、事業を行うための機械器具や材料、不動産といった有形財産はもちろんのこと、事業維持に欠かせないノウハウ等の無形財産などといった事業を構成するあらゆるものが含まれるのですが、そのうち何を譲渡対象とするのかは譲渡人と譲受人の当事者間の協議により定めることになります。
もっとも、譲渡人のみで譲渡対象としうるのは、あくまでも譲渡人に権利が単独で帰属する財産のみです。つまり、第三者が関係する財産については、譲渡人が自由に譲渡することは不可能となります(例えば、リース資産やライセンスを受けている権利などは譲渡不可。なお、労働者も当然に譲渡対象となるわけではありません)。
また、第三者に対して負担する債務についても、当然には移転しません。しかし、譲渡人が当該事業で用いていた“看板(屋号を含めた商号)”を譲受人がそのまま用いた場合、対外的には営業主が変わったようには見えません。このため、譲受人において看板を続用した場合は、債権者に対して債務を負担する可能性があること注意が必要です。
会社分割について
次に、会社分割ですが、第三者が関係する財産について、第三者の意向を無視して強制的に事業を譲受ける側に移転させてしまう事業譲渡(営業譲渡)の強化版とイメージすれば分かりやすいかもしれません(なお、第三者=労働者の場合は特別法による規制がありますので、当然に移転するわけではありません)。
ただ、ご留意いただきたいのが、会社分割の場合、“当該第三者の意向”に関わりなく承継されるのですが、“全て”の契約関係が承継されるわけではありません。非常に細かい話になってしまうのですが、実は、会社分割の対象となる事業部門と取引のある当該第三者のうち、契約関係を承継させるか否かは、会社分割の当事者が決めることができる、つまり会社分割契約書(新設分割の場合は新設分割計画書)に記載された当該第三者のみ承継がされる、というのが法制度になっています。
したがって、会社分割契約書等において、承継対象とされてしまった当該第三者については、その意向に関わりなく、事業を吸収する側の法人と契約関係が承継されるというのが正確な内容となります。
会社分割は上記の通り、たとえ第三者の意向に反しても強制的に第三者が関係する財産を移転させるものであるため、法律上の規制が厳しくなります。事業譲渡が原則的には当事者間の協議で進めることができることと比較すると、会社分割は厳格かつ柔軟性をやや欠く制度と言えるかもしれません。
結局のところは、事業を引き渡すに当たり、事業を維持継続するために必要となる第三者が関係する財産について、当該第三者の意向を考慮しながらどちらの手法を採用するのか検討することになります。
事業譲渡と会社分割について
ちなみに、事業譲渡の場合、事業を譲り受ける側の法人内部に事業譲渡の対象となる一事業部門を吸収することになります。しかし、当該事業部門にどのようなリスクが潜んでいるのか、調査し尽くしても分からないことが多く、いきなり自社内に吸収することに抵抗を持つこともあります。
一方、会社分割の場合、吸収分割という手続きであれば自社内に事業を吸収することになりますが、新設分割と呼ばれる新たな受け皿法人(この受け皿法人については事業を譲り受ける側が支配できるよう株式持分の調整を行う必要があります)を作り、そちらに当該事業部門を移すということもできます。
したがって、吸収する事業部門に潜むリスクを遮断したいのであれば、会社分割の一類型である新設分割を行ったほうが無難となります。
上記のような一事業部門を第三者に引き継いでもらった後、残った事業部門を含む会社だけでは事業継続が困難となりますので、清算手続きを図ることになります。そして、通常清算手続きを行うことが困難な場合、会社については破産手続きを行わざるを得ませんが、こうなってしまうと気になるのが社長(オーナー)の対応です。
経営者保証ガイドラインを用いて債務整理を図ることができるのであれば、社長(オーナー)の自己破産は免れることができ、自宅等を残せる可能性も出てきます。しかし、経営者保証ガイドラインの要件を充足しなかった場合は残念ながら自己破産手続きを選択せざるを得ないこととなります。
経営者保証ガイドラインの利用可否については、前もって専門家に相談しないと実際には難しいところがあります。社長(オーナー)におかれましては、早めのご決断をお願いしたいところです。
|
|
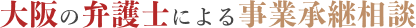
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一
