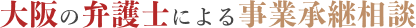事業承継における株式譲渡の方法とは
【ご相談内容】
事業承継を行うに際しては経営権の譲渡、すなわち株式を如何にして後継者に安全かつ迅速に譲渡することができるのかがポイントになると聞き及びました。
株式譲渡を行う方法とその注意点について、法務視点からのポイントを教えてください。
【回答】
現経営者が後継者に対して株式を譲渡しようとする場合、生前に譲渡したいと考えるのか、死亡するまで譲渡させないと考えるのかによって、その方法が大きく異なってきます。
すなわち、生前に譲渡使用する場合、①売買、②贈与の2つの方法が考えられます。
一方、現経営者が死亡するまで譲渡は行わないとなると、③相続の問題として処理することになります。
以下では、現経営者がどのように考えるのか場面に分けて検討します。
【解説】
生前に譲渡しようとする場合
(1)法的有効性と税務上のネック
この場合、現経営者が保有する株式を後継者が有償で買い取る「売買」という方法と、現経営者が保有する株式を後継者に無償で譲り渡す「贈与」という方法の2種類が考えられます。
ところで、どちらの方法を検討する場合であっても、“カネ”の問題を意識する必要があります。
すなわち、いずれの方法を選択しても、法的には現経営者が保有する全株式を1回で譲渡することは可能です。
しかし、売買を選択した場合、後継者の資金繰りを考慮し、株式の時価額より低い金額で売渡したとなると、税務上は贈与とみなされ、後継者に贈与税が賦課されるリスクが生じます。
そして、贈与の場合、株式の時価額から非課税枠(110万円/年)を超えた部分につき贈与税が賦課されます。
結局のところ、後継者は、贈与税が賦課されないように時価額にて株式を買取るだけのまとまった資金を必要とすることになります。もし資金を準備できない場合、数回に分けて株式買取を実行する、贈与の非課税枠を考慮した暦年贈与を実行するといった、後継者は一定の時間をかけて株式を譲受けることになります。ただ、現経営者の健康問題を意識せざるを得ず、果たして時間をかけてよいのかという視点は常に意識する必要があります。
(2)売買を選択した場合の注意点
上記(1)で解説した通り、現経営者が保有する株式の時価額に見合った買取資金が無いことには、1回で全株式を譲受けすることができません。また時価額より低廉な価格で売買を実行すると、後でみなし贈与として贈与税が賦課されることになります。
したがって、現経営者が生存中に株式譲渡を売買にて実行する場合、買取資金の有無は必須の検討事項となります。
ところで、買取資金の有無はあくまでも税務上の考慮要素に過ぎません。
すなわち、法的には買取資金が不足する=時価額より低廉な価格で株式を売買することは、現経営者と後継者が納得する限り何ら支障はなく、法的有効性を維持することが可能です。このことから、金額如何に関わらず、株式の売買を先に実行し、法的には株式を後継者に譲渡するといった作戦を実行することも一応考えられます。
ただし、この作戦を実行する場合、将来的には次のような問題が生じうることに留意する必要があります。
①みなし贈与税の問題(年度末の3月15日に贈与税の支払い時期が来ることを考慮すると、株式売買時期より後に贈与税の支払い時期が到来するので、その間に資金を準備する等の対策が必要と考えられます)
②特別受益の問題(現経営者が死亡し相続が発生した場合、他の相続人より「相続人である後継者は生前に実質無償で財産を譲受けており、その点を考慮せずに遺産分割するのは不公平だ」と主張されてしまうリスクがあります。特別受益の主張が認められた場合、後継者は株式以外の相続財産を本来の法定相続分以下でしか取得できないことになります)
(3)贈与を選択した場合の注意点
(年度末の3月15日の贈与税納税を考慮しつつ)どうしても買取資金が準備できない場合、株式の贈与を選択することになります。
一般的には、1年度当たり110万円までなら非課税となることを考慮し、株式の時価額との兼ね合いで数年に渡って少しずつ株式を譲渡する(いわゆる暦年贈与)という方法が用いられていますが、これはあくまでも税務面での考慮に過ぎません。上記の売買でも記載した通り、法的には、全株式を贈与することは全く問題なく有効に実施することが可能です(但し、相続開始時に特別受益の問題が生じうること前述の通りです)。
ところで、本記事作成時点では、贈与については税務面での特例措置が講じられていることに注意が必要です。すなわち、後継者(受贈者)が、現経営者(贈与者)より贈与を受けた会社の非上場株式について、納付するべき贈与税額のうち、発行済議決権株式の3分の2までに対応する贈与税額につき、その納税が猶予される制度が導入されています(いわゆる事業承継税制)。したがって、この事業承継税制の適用要件を充足するのであれば、贈与税を納税するための資金準備を行う必要がなくなりますので、一気に株式を生前贈与することが可能となります。税理士の中には相続関係は得意ではないという方も少なからずいるようですので、顧問税理士が不得手な場合は別の税理士を探したほうが得策かもしれません。
また他にも、後継者(受贈者)が2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、現経営者(贈与者)が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度である、相続時精算課税制度を用いて、とりあえず株式譲渡を先に実行し、株式を後継者に法的に帰属させることで相続時の株式トラブルを防止することも考えられます(当然のことながら将来発生する相続税のための納税資金を準備する必要があります)。
現経営者や後継者の中には、暦年贈与以外の税務問題の解消措置を知らないという方も結構多いようですので、適切な情報収集と専門家のアドバイスをもとに、後継者へ株式を贈与することを検討してほしいところです。
(4)生前に譲渡する場合の会社内手続きに注意
現経営者が100%株式を保有しており、後継者に100%株式を譲渡するという場合であれば問題が生じにくいのですが、現経営者の配偶者や親族等が少数ながら株式を保有し、取締役に就任しているという中小企業は意外と多いように思われます。
この場合、現経営者と後継者の二当事者間での株式譲渡取引(売買又は贈与)は、その当事者間では有効であるものの、法律上は第三者=当事者ではない会社との関係で当然に有効となるわけではないということを理解しておく必要があります。
すなわち、多くの中小企業の定款では株式譲渡を制限すること、会社が株式譲渡を承認しない限り会社は後継者(株式譲受人)を株主として取扱う必要がないことが定められています。そこで、会社の承認を取得する必要があるのですが、よくある勘違いは現経営者=代表取締役が株式譲渡に同意している以上、会社が承認していると考えてよいというものです、これは残念ながら明らか誤りとなります。なぜなら、会社法では、取締役会設置会社では取締役会にて承認を行う、取締役会非設置会社では株主総会にて承認を行うことが原則であると定められているからです。そして、大きな落とし穴となるのが取締役会設置会社の場合です。取締役会で株式譲渡の承認決議を行うことになるのですが、この決議の際、株式譲渡人である現経営者、株式譲受人である後継者は、たとえ取締役であっても決議に参加することができません。これは特別利害関係に該当するからなのですが、理屈はともかく、結果的には現経営者・後継者以外の取締役のみで株式譲渡の承認の可否を決めることになります。万一、現経営者・後継者以外の取締役が株式譲渡の承認に反対した場合、会社は承認しないという取扱いになるため、法的には会社は株式譲渡人である後継者を株主として取扱わないことになります。
中小企業の場合、株式譲渡に対する会社の承認手続き自体が履行されていないことも多いのですが、後で、特に相続の場面などにおいて、手続き違反を指摘され後継者の立場が苦しくなるといったこともあったりしますので、要注意の事項となります。
会社の承認の取得の仕方、他の取締役が反対している場合の対処法などは、色々と法律を駆使して対処する必要があるため、是非弁護士に相談してほしいところです。
なお、取締役会非設置会社の場合、会社の承認の有無は株主総会決議で決めることになるところ、現経営者及び後継者は株主であっても、特別利害関係人として決議より排除されることありませんので、ご安心ください。
2.生前に譲渡しない場合(現経営者死亡まで譲渡しない場合)
(1)株式を相続した場合
株式は相続財産として相続の対象となります。
ただ、世間一般で誤解が多いのですが、法定相続分に従って当然に分割されるわけではありません。例えば、相続人が配偶者と子2人、相続の対象となる株式が100株である場合、配偶者は50株、子供は各25株ずつ当然に取得するわけではありません。
非常に分かりづらいかと思うのですが、次のような状態となります。
・株式は相続人の準共有となる。
・遺産分割協議を経て、誰が株式を取得するのか決める。
・遺産分割協議が未了の場合において株主として権利行使する場面が生じた場合、相続人間で協議して権利行使者を選出し、その者が代表して権利行使する。
・協議により権利行使者を選出できない場合、持分価格(=法定相続分)の過半数により権利行使者を選出する。
例えば、後継者が長男である場合、遺産分割協議により長男に全株式を集中帰属させることができれば問題ないのですが、これができない場合、被相続人の配偶者ともう1人の子供が結託することで権利行使者を意のままに選出することができ、株主総会を牛耳ることが可能となります。このため、後継者は自由に経営ができず、場合によっては会社から追い出される可能性さえ出てきます。
このような事態が想定されうることから、現経営者の皆様におかれましては、「あとは遺産分割で決めればよい」なんて安易に考えないでほしいところです(残された者たちは仲が良いので揉め事は起きないという考えも禁物です)。
(2)遺言書による対応
現経営者の考えとして、生前中には特に対策を講じるつもりはない、しかし自分の死後に後継者争いが生じることは望ましくないとする場合、遺言書を作成し、株式を後継者に相続させる旨定めておくという方法が考えられます。
なお、どうせ遺言書を作成するのであれば、自筆証書遺言ではなく、公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することをお勧めします。たしかにお金はかかりますが、遺言書作成時の遺言能力、紛失・偽造リスク等について、格段に低減し、遺産分割協議時に「あの遺言書は無効だ」という争いをかなりの確率で防止することができるからです。
ところで、遺言書を用いて株式を後継者に相続させる場合、世間一般でもある程度知られるようになってきたのですが「遺留分」について気を遣う必要があります。特に、被相続人の資産の大部分を株式が占めるという事例は少なからず存在するのですが、こういった場合は遺留分侵害問題が必然的に生じてしまいます。
2019年の法改正により、遺言書で誰が株式を相続するのか指定することで、指定された者(後継者)は株式それ自体を確実に取得できるようになったものの、他の相続人に対して遺留分侵害に相応する金銭支払い義務を負担することになります。もちろん後継者が支払うだけの資金を保有しているのであれば大きな問題とはならないものの、当該資金を有していないという事例も数多く見かけます。
遺言書で株式を譲渡しようと考えているのであれば、遺留分侵害の有無に気を払うことはもちろん、遺留分侵害の場合に備えた後継者への資金融通(例えば生命保険を活用した資金の確保など)も考慮の上、対策を講じたいところです。
(3)遺言信託(金融機関)の注意点
世間ではかなりの確率で誤解されていると思われるのですが、弁護士や税理士等が提案する「信託(家族信託など)」と、金融機関が提案する「信託(遺言信託)」は似て非なるものとなります。
金融機関が提案する「信託(遺言信託)」は、遺言者(現経営者)が作成した遺言書を預かり保管し、相続開始後、遺言執行者に就任して遺言書の通りに相続財産を分配する事務作業を行うことを内容としたサービスとなります。このように書くと、金融機関が遺言書記載内容に従って、相続財産を分配してくれるのだから問題ないのでは…と思われるかもしれません。しかし、前述の遺留分侵害の問題が発生した場合、あるいは遺言書の作成能力に相続人が疑義を呈した場合、その他遺産分割協議について紛争が生じた場合、金融機関は遺言執行者に就任することを拒否します。この結果、遺言書は宙に浮いた状態となり、結果的に相続人による紛争が激化するという事態を招いたりもします。
要は、金融機関が提案する「信託(遺言支度)」は、相続問題が解決するまで面倒を見てくれるわけではないことをよく理解しておく必要があります。
一方、弁護士や税理士等が提案する「信託(家族信託など)」は、信託法に基づく財産管理制度のことをいいます。あくまでも現経営者が生存中に、株式の処分等を第三者に託し、託された第三者が生存中はもちろん死後においても、託された内容に従って株式の処分等を行っていくというものです。
現経営者が生存中に信託により株式を処分することになるため、実のところは生前中の株式譲渡と捉えたほうが分かりやすいかもしれません(なお、理屈の上では、遺言書の内容として信託を行うことも可能です。この場合、相続開始時に信託が開始することになります)。
ちょっと分かりにくい制度かと思いますが、後述するような株式は信託譲渡するものの、株主権(議決権)は現経営者が保持したままといった取扱いもできたりするため、現経営者の思いを柔軟に解決できる可能性を秘めた制度といえます。
詳しくは弁護士等に相談してください。
3.経営権を残したまま株式譲渡する方法
事業承継対策を行う必要性は理解していても、現経営者が実行に躊躇する1つの理由として、株式を手放してしまったら経営に一切関与できなくなってしまうことへの不安があげられます。
そこで、経営権=議決権を現経営者に留保しつつ株式を譲渡する方法につき、簡単に解説します。
(1)信託(家族信託など)を利用する方法
前記2.(3)でも触れましたが、例えば、委託者を現経営者、受託者を後継者、受益者を現経営者とする信託契約を締結し、株式を現経営者から後継者へ(信託的に)譲渡した場合、受託者は委託者の指図に従って議決権を行使する義務が生じます。
信託(家族信託など)を用いれば、このような経営権を現経営者に留保しつつ、株式譲渡を実現することが可能となります。また、上記例の場合、委託者と受益者が現経営者であることから、実は贈与税も発生しません。
非常に便利な制度なのですが、あまり世間一般では認知されておらず、利用状況は芳しくないというのが実情です。ただ、せっかく本記事を読まれたのであれば、信託(家族信託など)という制度があることを知って頂き、自分の事例でも適用ができるのか、是非弁護士等の専門家に相談してほしいところです。
(2)種類株式を利用する方法
種類株式を利用する方法の代表的なものは、一定の事項につき拒否権を持つ種類株式を現経営者に発行し、現経営者が保有する普通株式を後継者に譲渡することで、日常的な経営判断は後継者が行えるものの、重要な経営判断が必要となる事項については現経営者が株主総会で拒否権を発動し、会社経営に影響力を及ぼすことができるといったものとなります。
現経営者が保有する株式に包含される複数の権利の内、一部だけを譲渡し・保留するといった信託による譲渡では問題があるという場合、上記のような方法は検討に値します。
なお、拒否権付の種類株式は1株だけ発行すればよいところ、現経営者が死亡した場合に備えて、定款に相続が発生した場合に会社による株式買取請求権を定めておけば、会社は多大な負担を強いられることなく当該種類株式を買取ることが可能です(但し、分配可能額の範囲内という財源規制があります)。したがって、遺産分割時に種類株式を巡って紛争が生じることも事前に防止することが可能です。
(3)属人的株式を利用する方法
特定の株主に対して、他の株主とは異なる取扱いを認めるというものなのですが、例えば、現経営者が保有する株式については1株当たり10議決権を付与する、他の株主については原則通り1株当たり1議決権とする、といった取扱いを行うことが可能です。
このような事例の場合、現経営者が100株保有しているのであれば、90株を後継者に譲渡し、10株を現経営者が引き続き保有することで、現経営者は議決権の過半数を維持することが可能となります(現経営者は100個の議決権を有するため)。
なお、現経営者が死亡した場合、1株当たり10個の議決権という特例は認められなくなりますので、後継者は議決権の9割を握ることとなり、安定的な経営を行うことが可能です。ただし、現経営者が保有していた10株については当然に後継者には帰属しない以上、遺産分割協議を通じて取得を試みなければならないというデメリットは残ってしまうことに注意が必要です。
<2022年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。